「ラブリコでおしゃれな棚を作ってみたけれど、ちょっと不安…」「この棚、本当に何キロまで大丈夫なの?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
SNSやDIYブログでも話題の【ラブリコ(LABRICO)】は、賃貸住宅でも壁や天井を傷つけずに棚や仕切りを作れる便利アイテム。
木材とセットで突っ張るだけという手軽さで、多くのDIY初心者にも人気を集めています。
しかし、その手軽さゆえに「棚が落ちた」「突っ張り柱が倒れた」「推しグッズが落下して破損した」といったトラブルが起きているのも事実。
耐荷重を正しく理解せず、見た目だけで設置してしまうと、思わぬ事故やケガにつながる可能性もあるのです。
この記事では、ラブリコの耐荷重にまつわる正しい知識や安全対策を徹底的に解説。
公式スペックから設置場所・素材・補強方法にいたるまで、初心者でも失敗しない「安全なDIYのポイント」をわかりやすくまとめました。
さらに、実際にあった落下事例や補強アイテムの紹介も含め、読んだその日から安心してラブリコを使えるようになります。
「推し活用の棚を作りたい」「壁面収納を増やしたい」「でも安全性もちゃんと気になる」
そんなあなたにこそ読んでほしい内容です。
ラブリコの耐荷重ってどれくらい?公式スペックをチェック
DIY初心者にも人気の突っ張りアイテム「ラブリコ」。
使い方は簡単で、ツーバイフォー材に専用のアジャスターを取り付け、床と天井に突っ張るだけ。釘もネジも不要で壁を傷つけないため、賃貸でも気軽にDIYが楽しめます。
ただし、見た目の安定感とは裏腹に、実際にどれくらいの重さに耐えられるのか?という点が非常に重要です。
「本や雑貨を置いたら、棚板が傾いてきた…」「突っ張りが甘くてグラグラする」など、耐荷重を知らずに使うことで起こるトラブルは意外と多いのです。
● ラブリコの基本耐荷重は「柱1本あたり20kg〜40kg」が目安
ラブリコ公式が公開している情報によると、2×4材(ツーバイフォー)用のアジャスターを使用した場合の耐荷重は、1本の柱あたり約20kg程度。
ただしこれは理想的な設置環境(平らな天井・しっかり突っ張れる構造)での数値であり、実際には使用状況や荷重のかかり方によって大きく変動します。
また、棚受けやパーツの形状・設置位置も耐荷重に影響を与える重要な要素です。
たとえば、ラブリコの「棚受けパーツ」は1組で約5〜10kg程度が目安とされており、重たいものを置くには“柱の本数”や“棚板の長さ”も工夫が必要になります。
● ディアウォールとの違い|耐荷重で選ぶなら?
ラブリコと並んで人気の「ディアウォール」との比較でよく出てくるのが、耐荷重に関する違いです。
ディアウォールは内蔵バネによる突っ張り構造のため、「ラブリコよりやや固定力が高い」という口コミもありますが、実際の耐荷重は使用環境によって差が出るため、必ずしも「どちらが上」とは言い切れません。
ポイントは、いずれも“DIY用仮設構造”であり、重すぎるものを乗せることは想定されていないという点です。
つまり、ラブリコ・ディアウォールに共通する注意点は「強度を過信せず、補強を前提に考えること」。
● こんな誤解に注意!
「柱2本あるから40kg載せても大丈夫だよね」と思ってしまいがちですが、これは重さが均等に分散された場合に限った話。
重心が偏ったり、上下に揺れる振動が加わると、想定外の負荷がかかって一気に崩れるケースも。
特に観葉植物や水槽、家電など“重量+液体+振動”の組み合わせは危険度が高いため注意が必要です。
● 結論:耐荷重は「過信せず控えめに」が安全
ラブリコの構造自体は非常にシンプルで扱いやすい反面、耐荷重の考え方を間違えるとトラブルの原因になります。
安全に使うためには…
- 柱1本あたり20kg以下を目安にする
- 棚受けパーツの強度も確認する
- 重いものを置く場合は、柱を3本以上にする
- 滑り止めマット・補強金具などを併用する
といった対策が重要です。
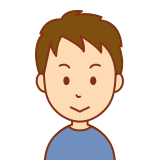
耐荷重を知って安心DIYを始めよう!
落下・破損を防ぐための注意点|よくある失敗とその対策
ラブリコを使ったDIYは手軽で楽しい反面、「棚が落ちてきた」「支柱が傾いた」といったトラブルも少なくありません。
特に耐荷重や設置環境を軽視してしまうと、思わぬ破損やケガにつながるリスクがあります。
このセクションでは、ラブリコ使用時によくある失敗例と、それを防ぐためのポイントを詳しく解説します。
● NG例①:突っ張りが甘い or 設置面が不安定
ラブリコは天井と床で柱を突っ張る仕組みのため、設置面がフラットでない場合や、突っ張りが甘い場合は一気に安定性が崩れます。
特に注意したいのは以下のようなケースです。
- 天井が石膏ボードや板張りで柔らかい
- 床が畳・カーペットなど沈む素材
- 築年数が古く、天井の水平が取れていない
- 柱の長さが正確でない(±1mmでもズレると弱くなる)
突っ張りが不十分だと、柱がズレて倒れる or ゆっくり滑り落ちてくる危険性があります。
▶対策
- 柱の長さは「設置高 – 95mm(ラブリコ使用時)」で正確にカット
- 天井と床に【滑り止めシート】を挟む
- 木材が歪んでいないか、水平器で確認
- 設置後は力を加えてもズレないかチェック
● NG例②:重心の偏りや“片寄せ”設計
棚板に重いものを片側だけに載せたり、柱の片側に収納が偏っていると、重心がズレて不安定になりやすくなります。
とくに横長の棚や、一方向に本や家電を積む構造では、支柱のねじれや棚受けの歪みが起きやすくなります。
▶対策
- 棚には左右バランスよく配置する
- 重いものほど下段に置く
- 棚板をL字金具などで補強する
- 柱を左右対称に複数設置する(最低2本、できれば3本)
● NG例③:想定外の揺れや振動
ラブリコは「地震対応の家具」ではありません。強い揺れや振動には耐えられない構造です。
- 地震時の横揺れで棚が崩れる
- 音楽機材の振動、子どもがぶつかる、掃除機の接触など
- 推しグッズの飾り棚で「落下→破損」するケースも…
▶対策
- 耐震ジェルパッドやL字金具を使って壁・棚を補強
- 倒れると危険なもの(観葉植物・ガラス製品・水槽)は避ける
- 収納棚には扉やガードを付けて落下防止
● NG例④:そもそも木材の品質が低い
ツーバイフォー材は安価で入手しやすい反面、反りや割れがあることも。特に安売りの木材では、そもそも突っ張りに向いていない材質の場合もあります。
▶対策
- 木材はホームセンターで「反り・割れのないもの」を選ぶ
- できれば「構造用」「乾燥材」など強度の高いものを選択
- 使用前にヤスリがけ&防腐・保護処理も忘れずに
● 安全第一で、構造と重さをシビアにチェック!
DIYは自由で楽しい反面、構造物には必ず“重力”と“安全性”が関わってきます。
「これくらい大丈夫だろう」と思っていた重さでも、時間が経つとたわみが出たり、柱の突っ張りが緩むこともあるのです。
ラブリコを使うときは、
- 使用環境を客観的にチェック
- 重さやバランスをシミュレーション
- 必ず設置後にグラつきチェック
この3つをセットで実行することが、DIYを楽しく続ける最大の秘訣です。
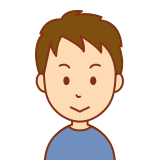
複数の柱で安定感がアップ!
安全に使うための補強テクニック|“倒れないDIY”のための工夫いろいろ
ラブリコを使った突っ張り棚や壁面収納は、見た目もスッキリしておしゃれ。
でも、「ちゃんと補強されていないDIY」は、どんなにきれいでも安全性に不安が残ります。
特に賃貸住宅やお子様のいる家庭では、落下や転倒を未然に防ぐための「+αの補強」がとても大切です。
ここでは、実際に多くのDIYerが取り入れている「ラブリコをより安全に使うための補強テクニック」を厳選してご紹介します。
● テクニック①|棚板の“たわみ”を防ぐ「補強金具」の活用
ラブリコと2×4材だけで棚を作った場合、棚板がたわんで中心部が沈むことがあります。
本や調理家電など、重さがあるものを載せると数日でたわみ始め、ゆがみや崩落の原因にも。
▶対策
- 棚板の下に「L字金具」「山形アングル」「フラットバー」を取り付けて補強
- 中央にも柱を1本追加して“中継支柱”を設置
- 板の厚みは18mm以上の合板・集成材が◎
目安としては、60cm以上の幅の棚板には必ず補強を入れるのがおすすめです。
● テクニック②|突っ張りのズレを防ぐ「滑り止め+隙間対策」
突っ張り部分(上下)にかかる力は意外と強く、少しのズレや傾きでもグラつきの原因になります。
▶対策
- 天井&床との接地面に【滑り止めシート】を敷く
- 天井に段差がある場合は「水平パッド」「クッション材」で調整
- ラブリコの下に「床保護マット」を敷いてズレ&傷を防止
特にフローリングの上に直接置く場合は滑りやすいため、滑り止め対策は必須です。
● テクニック③|振動や揺れに備える「耐震グッズ」の併用
ラブリコは“仮設構造”であり、地震対応の家具ではありません。
倒れやすい構造物には、耐震対策をプラスしましょう。
▶対策
- 【耐震ジェルパッド】を支柱の上下に貼る
- 棚の裏に「L字固定金具」で壁とつなぐ(ビスが打てる場所限定)
- 棚板の縁に「落下防止バー」や「前面ガード」を取り付ける
- 装飾品は【耐震マット】で固定する
揺れに強くなるだけでなく、日常生活の中での「子どもの衝突」「掃除機が当たる」などの事故も防げます。
● テクニック④|安全+おしゃれを両立する「有孔ボード×補強」
有孔ボード(ペグボード)を組み合わせることで、見た目を損なわずに補強が可能になります。
▶対策
- 有孔ボードを背面に取り付けて、構造に“面”を持たせる
- フックやカゴを自由に付けられるため、収納力もアップ
- ボードで全体をつなげることで、揺れ・横ズレに強くなる
棚+有孔ボードで壁面収納を作れば、見せる収納×安全性のバランスも◎。
● テクニック⑤|柱の本数を増やす&均等に配置
2本の柱でも棚はできますが、強度やバランスを考えるなら“3本以上”が理想です。
▶対策
- 100cm以上の棚板なら、柱は3本配置
- 両端+中央に支柱を置き、全体のバランスを取る
- 柱を「壁の間柱の位置」に合わせて設置すると、より安定しやすい
柱の本数を増やすと見た目がゴツくなるデメリットはありますが、安全性と引き換えと考えれば価値があります。
安全性は「後付け」で高められる!自分と家族を守るDIYを
どんなにおしゃれで便利な収納でも、落ちてきたら台無し。
ましてや、ケガや家具破損を引き起こすようなDIYでは本末転倒です。
ラブリコは「初心者でも使いやすい」からこそ、しっかりと補強してこそ真価を発揮するアイテムです。
次は、実際に多くのユーザーが実践している「アイデア実例集」をご紹介します。
オシャレと実用性を兼ね備えた活用術、見ていきましょう!、長期間安全にDIYを楽しむことができます。
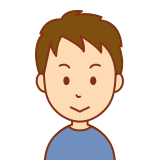
補強でさらに安心してDIYを!
活用アイデア実例集|ラブリコで叶える“魅せる収納”と空間アレンジ
ラブリコを使ったDIYの魅力は、なんといっても「アイデア次第で無限に広がる自由な使い方」。
ここでは、実際に多くのユーザーが実践している人気の活用法を厳選してご紹介します。
「便利」「おしゃれ」「賃貸でもOK」なアイデアばかりなので、自分のライフスタイルに合ったものをぜひ見つけてみてください。
● ① 壁一面の“見せる本棚”でカフェ風リビングに
突っ張り式の柱を3本以上設置し、幅広の棚板を等間隔で並べれば、本格的な壁面本棚が完成。
お気に入りの小説、アートブック、雑誌を並べて「見せる収納」にすれば、それだけでカフェのような空間に。
さらに、読書灯や観葉植物、写真フレームなどをアクセントに加えると、自分だけの“くつろぎのコーナー”が生まれます。
▶おすすめポイント
- 書斎やリビングのアクセントに最適
- 雑誌やアートも飾って「見せる棚」に
- 柱と棚板の色を統一すると一気におしゃれ感UP
● ② キッチン収納ラックで“調理の動線”が快適に
キッチン周りは「収納が足りない」「ゴチャつく」が定番の悩み。
そんな時こそ、ラブリコで“壁面収納ラック”を設置して、スパイスや調理器具、カトラリーをスッキリまとめましょう。
棚板の奥行きを浅めにすれば、圧迫感も少なく、狭いキッチンでも活用可能。
S字フックやワイヤーバスケットと組み合わせることで収納力がぐっと上がります。
▶おすすめポイント
- コンロ横・シンク上のデッドスペースを有効活用
- ラックを使えば調理中の動線がスムーズに
- おしゃれな調味料瓶を並べて“映えるキッチン”にも
● ③ 洗面所のタオル&ケアグッズ収納に
意外と活躍するのが「洗面所」や「脱衣所」。
突っ張り柱+棚板で、タオルやドライヤー、洗剤などをスッキリ見せながら収納できます。
ラブリコのナチュラルな木目カラーは、白を基調とした洗面空間とも相性抜群。
雑貨店のようなおしゃれな空間に早変わりします。
▶おすすめポイント
- スペースが限られた場所でも設置しやすい
- バスケット収納で整理整頓が簡単に
- タオルの色を統一すると一気にホテルライクに!
● ④ “飾るだけ”じゃない!作業デスクやPCコーナーにも
ツーバイフォー材で天板を設置し、L字金具で補強すれば、ラブリコで“簡易デスクやワークスペースも作れます。
ノートPC・LEDライト・小型スピーカーを並べれば、自宅での作業や在宅ワークも快適に。
デスク下に引き出し収納をつければ、見た目もスッキリ。
▶おすすめポイント
- カフェ風のワークデスクがDIYできる
- テレワーク・趣味の作業場にぴったり
- 椅子の高さに合わせて天板の高さを調整可能
● ⑤ 子ども部屋の“成長に合わせて変えられる”収納棚
子どもの成長に合わせて収納ニーズは変わるもの。
ラブリコで作った棚は、棚板の高さを変えたり、パーツを付け足したりしやすいため、まさに「育てられる収納」。
おもちゃ、絵本、ランドセル、習い事グッズまで…すべて一元管理できます。
▶おすすめポイント
- 棚板の高さを変えられる=成長にフィット
- 色を塗ったりステッカーでカスタマイズもOK
- 将来は“大人仕様”に作り替えることもできる
あなたらしい“ラブリコ空間”を、自由に楽しもう
ラブリコは、ただの「突っ張りグッズ」ではありません。
アイデアとちょっとの工夫で、あなたの暮らしにフィットする収納・インテリアが自由自在に作れる魔法のアイテムなんです。
DIY初心者でも、賃貸住まいでも、センスがなくても大丈夫。
「こんな空間があったらいいな」という想いを、少しずつカタチにしていけることこそ、ラブリコの一番の魅力です。
ラブリコでテレビを設置する際の耐荷重と安全対策
ラブリコは、壁や天井を傷つけることなく柱を立て、DIYで空間をカスタマイズできる便利なツールです。賃貸住宅や壁に穴を開けたくない場所での使用に最適です。特にテレビを設置する場合は、ラブリコの耐荷重を正しく理解し、安全に設置するための対策を講じることが必要です。この記事では、ラブリコを使用してテレビを設置する際の耐荷重のポイントと安全対策について詳しく解説します。
ラブリコの耐荷重の基本
ラブリコの耐荷重は、1本の柱でおおよそ10〜20kgとされています。テレビを設置する際には、テレビ自体の重量とその他の要因を考慮して、複数の柱を使用することが推奨されます。これにより、荷重が均等に分散され、安定感が向上します。テレビのサイズや重量に応じて、必要な柱の本数を検討しましょう。
テレビ設置時の耐荷重のポイント
- テレビの重量確認:設置予定のテレビの重量を確認し、それに基づいて必要な柱の本数を決定します。例えば、40インチのテレビは10〜15kg程度であることが多いため、2本以上の柱で支えることが望ましいです。
- 追加のサポート:テレビを安全に設置するために、棚受けや補強金具を使用することで、柱にかかる力を分散し、耐荷重を向上させることができます。
テレビを安全に設置するための柱配置
テレビを設置する際には、柱の配置が重要です。適切な間隔で柱を設置し、荷重が均等に分散されるようにします。ラブリコを複数本使用することで、設置面が広がり、安定感が増します。柱の配置はテレビの幅に応じて調整し、中心からのバランスを保つことがポイントです。
棚受けと補強の活用
棚受けや補強金具を使用することで、テレビの重さを柱全体で支えることが可能になります。強度のある金属製の棚受けを柱に取り付け、テレビを安定させることで、揺れや荷重による柱の緩みを防ぎます。また、棚受けはテレビを取り付ける高さに設置することで、柱全体の安定性を確保できます。
耐荷重を超えると起こるリスク
ラブリコの耐荷重を超えた使用は、柱やテレビが倒れるリスクを伴います。特に、長時間にわたり重いテレビが設置されると、突っ張りの力が弱まり、柱が徐々に緩む可能性があります。
柱の緩みや倒壊のリスク
耐荷重を超えて設置を行うと、柱の突っ張りが耐えきれずに緩んで倒れるリスクが生じます。これは特に、設置場所が滑りやすい素材である場合や、重量が片側に偏っている場合に顕著です。設置後も定期的に柱の突っ張り具合を確認し、緩みが生じていないかをチェックしましょう。
テレビ設置時の安全対策
地震対策
日本は地震が多い国です。ラブリコを使用してテレビを設置する際には、耐震対策を講じることが重要です。テレビの下部に耐震マットを敷き、揺れが発生した際のズレを防ぐと共に、柱と棚受けをしっかりと固定して揺れに備えることが推奨されます。また、耐震ストラップを使用して、テレビ自体を柱に固定することで、揺れによる倒壊リスクを大幅に軽減できます。
定期的な点検とメンテナンス
ラブリコを用いたテレビ設置後も、定期的に設置状況を確認することが大切です。柱の安定性、棚受けや補強金具の緩み、テレビの位置などをチェックし、必要に応じてネジを締め直すなどのメンテナンスを行いましょう。これにより、長期間にわたり安全に使用できます。
テレビ設置時に考慮する配置の工夫
設置するテレビの位置は、視聴のしやすさだけでなく、荷重のバランスも考慮する必要があります。柱に対して均等に荷重がかかるように配置し、特定の柱に負担が集中しないようにすることがポイントです。また、テレビの後ろ側に棚受けを設置し、背面の支えを強化することで、安定感がさらに高まります。
ラブリコを使ってテレビを設置する際には、耐荷重の確認と安全対策を徹底することが欠かせません。複数の柱を使用し、適切な補強を行うことで、テレビ設置をより安全に行えます。地震対策を含め、定期的なメンテナンスを怠らずに行うことで、ラブリコを使ったDIYの利便性を最大限に活かし、安心して生活空間を楽しむことができます。
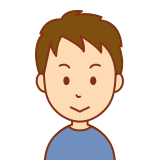
安全第一でテレビ設置を!
ラブリコの耐荷重を高める棚受けの選び方と設置方法
ラブリコは、賃貸住宅でも壁や天井を傷つけずに柱を設置できるため、多くのDIY愛好者に支持されています。しかし、重い物を載せる際には、耐荷重を強化するための工夫が必要です。特に、棚受けの選び方と設置方法を正しく行うことで、ラブリコの柱の耐荷重を高め、より安全に使用することが可能です。この記事では、ラブリコの耐荷重を高めるための棚受けの選び方と設置方法について詳しく解説します。
棚受けの選び方
棚受けを選ぶ際には、強度と素材が重要なポイントです。ラブリコの柱を使用して重い棚や物を支える場合、耐久性のある棚受けを選ぶことで、耐荷重を高めることができます。
耐荷重に適した素材
- 金属製棚受け: 強度が高く、重い物を支えるのに適しています。特にスチール製やアルミ製の棚受けは耐久性があり、長期間使用しても安定性を保てます。
- 木製棚受け: 美観に優れ、軽い物を載せる場合におすすめです。木製棚受けも適切に選べば強度を持ち、ラブリコの柱と調和したインテリアを演出できます。
サイズと形状の選定
棚受けは、取り付ける棚板のサイズや使用目的に応じて選びます。例えば、幅の広い棚には長めの棚受けを選ぶことで、棚板全体をしっかりと支えることができます。また、L字型やT字型などの形状を選ぶことで、荷重を柱に効率よく分散させることが可能です。
棚受けの設置方法
棚受けの設置は、柱の安定性と荷重のバランスを保つために慎重に行う必要があります。以下は、棚受けを効果的に設置するための手順です。
棚受けの位置を決定する
- 柱の間隔を測定: まず、ラブリコの柱を設置した後、棚板を取り付ける位置を決定します。柱の間隔は均等に保ち、棚受けを取り付けることで荷重が分散されるようにします。
- 水平を確認: 水平器を使用して、棚受けが水平になるように位置を調整します。棚が水平でないと、物が滑り落ちたりバランスを崩したりする原因となります。
棚受けの取り付け手順
- 位置をマーキング: 棚受けを取り付ける位置を柱にマーキングし、ネジを打つ場所を決めます。
- ネジで固定: 棚受けを柱にしっかりとネジで固定します。強度を高めるために、柱と棚受けをしっかりと固定できるネジを使用することが重要です。ネジの長さは棚受けと柱の厚さに応じて選びましょう。
- 棚板を設置: 棚板を棚受けに乗せ、ネジや固定具でしっかりと固定します。棚板が安定していることを確認し、再度水平をチェックします。
棚受けを使用した耐荷重の向上
棚受けを適切に選び、正しい方法で設置することで、ラブリコの柱の耐荷重を大幅に向上させることができます。棚受けは柱と棚板の接点で荷重を支える役割を果たし、柱全体に負荷を分散させる効果があります。特に、重い棚や大型の物を載せる場合は、複数の棚受けを使用して負荷を均等に分散させることで、安全性を確保できます。
安全な使用のための追加対策
滑り止めシートの活用
設置面が滑りやすい場合は、滑り止めシートを活用することで、棚や柱がズレるのを防ぐことができます。滑り止めシートを敷くことで、設置した棚がしっかりと固定され、耐荷重が向上します。
定期的な点検
ラブリコを使用した棚は、設置後も定期的に点検を行いましょう。棚受けやネジの緩みがないか、柱がしっかり固定されているかを確認し、必要に応じて補強や再固定を行います。これにより、長期間にわたって安全な状態を保つことができます。
ラブリコの耐荷重を高めるためには、棚受けの選び方や設置方法に注意を払い、適切な対策を講じることが重要です。金属製の強度ある棚受けを選び、正しい手順で設置することで、重い物を支える際の安全性が向上します。さらに、定期的なメンテナンスを行い、設置物の安定性を維持することで、快適で安全なDIY空間を作り出せるでしょう。
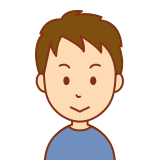
適切な棚受けで耐荷重を強化!
よくある質問Q&Aと注意点|ラブリコDIY前の不安をまるごと解消!
「賃貸でも本当に大丈夫?」「重いものを載せても平気?」
ラブリコを使ったDIYに挑戦したいけど、ちょっと不安…。そんな声も多く聞かれます。
ここでは、ラブリコ初心者が抱えがちな疑問とその答えをQ&A形式でわかりやすく解説します。加えて、やってはいけない注意点も丁寧に紹介するので、初めての人でも安心してスタートできます。
Q1. ラブリコって本当に「壁を傷つけず」に使えるの?
はい、基本的には壁・床・天井に穴を開けることなく設置できるのがラブリコ最大の特徴です。
ただし、設置する床や天井の素材によっては「凹み」や「摩擦跡」がつく可能性もあるため、滑り止めシートやクッション材を併用するとより安心です。
とくに賃貸で「原状回復」が必須な場合は、設置前にマスキングテープ+フェルトなどを活用するのがおすすめです。
Q2. 耐荷重はどれくらい?重い物でも大丈夫?
ラブリコの耐荷重は、
- 基本構造:柱1本あたり約20〜30kg(設置状態や木材の強度による)
- 棚板に載せる荷物の重さは軽めを意識が基本
重い本や家電などを載せる場合は、
- 柱の数を増やす(2本→3本へ)
- 棚受けにL字金具や金属ブラケットを使用する
- 重い物は必ず“下段”に配置する
など、重量バランスと補強の工夫がカギになります。
Q3. ツーバイフォー材ってどこで買える?自分でカットするの?
ツーバイフォー材はホームセンターやネット通販で手軽に入手できます。
多くのホームセンターでは「設置場所の天井高」を伝えれば、その場で正確にカットしてもらえるサービスもあるため、DIY初心者でも安心。ネットで購入する場合は、カットオーダー対応のショップを選ぶとスムーズです。
カット後は、ヤスリがけや防腐剤の塗布などの下処理も忘れずに行いましょう。
Q4. 木材の色や素材は自由に選べるの?
はい。基本的にラブリコはツーバイフォー(SPF材)に対応していますが、ペイントやステイン加工などで自由にアレンジ可能です。
インテリアに合った色味に塗装したり、木目調シートを貼ったりすることで、より自分らしい仕上がりになります。
最近は、あらかじめ「白・黒・ナチュラル」などの色付き木材も販売されており、加工の手間を省きたい方にもおすすめです。
Q5. ラブリコとディアウォール、どちらがいいの?
どちらも人気の突っ張りDIYパーツですが、以下の違いがあります:
| 項目 | ラブリコ | ディアウォール |
|---|---|---|
| 特徴 | 上部にバネとネジで微調整が可能 | 上下にスプリング内蔵 |
| 安定性 | 高め(細かな微調整が可能) | シンプルで設置が早い |
| 天井高の誤差 | ±2mmまで対応 | 厳密なカットが必要 |
| 見た目 | スタイリッシュで種類が豊富 | シンプルで無骨感あり |
初心者には「微調整しやすい=設置ミスが少ない」ラブリコの方が扱いやすいことが多いです。
ラブリコDIYで失敗しないための注意点まとめ
ラブリコを安全に、そして長く楽しむためには以下の点に注意しましょう:
- 突っ張りの強さを過信しない:ときどきグラつきチェックを!
- 重さと重心のバランスを常に意識:棚板の偏りNG
- 子どもやペットが触れる場所には安全対策を:転倒防止や角のガードなど
- 防災対策も忘れずに:耐震ジェル、L字金具の活用
- 定期的なメンテナンスを:ネジの緩みや木材の劣化は要チェック
DIYは「自由」であるからこそ、知識と安全性の確保がなによりも大切です。
ちょっとした確認と工夫で、あなたの理想のインテリアはもっと楽しく、もっと快適に近づきます。
まとめ|ラブリコで“理想の空間”を手に入れよう
DIYに興味があるけれど、賃貸だからと諦めていませんか?
「壁に穴は開けられない」「原状回復が心配」「そもそも工具を持っていない」──そんな悩みをまるごと解決してくれるのが、突っ張り式DIYアイテム「ラブリコ」です。
ラブリコなら、壁や天井を傷つけずに、誰でも簡単におしゃれで実用的な棚や仕切りを作ることができます。
しかも見た目はすっきりスタイリッシュ。DIY初心者にもやさしく、日常の中に“自分らしさ”を取り入れる絶好のツールです。
この記事では、ラブリコの耐荷重や安全性、設置方法、補強の工夫、そして実際の活用アイデアまで、余すことなく解説しました。
今まで不安で一歩踏み出せなかった方も、「これならできるかも」と感じられたのではないでしょうか?
ラブリコDIYが叶えてくれるのは、ただの収納スペースではありません。
それは「暮らしを自分の手で整える心地よさ」であり、「制約のある環境でも、工夫で乗り越えられる自信」でもあります。
まずは、設置したい場所を決めて、1本の木材から始めてみましょう。
やがてその1本が、部屋の雰囲気を変え、あなたの暮らしに心地よい変化をもたらしてくれるはずです。
ラブリコで、あなたの“理想の空間”を、ぜひ一歩ずつ形にしていってください。
その小さな一歩が、日常に大きな彩りを添えてくれることでしょう。


コメント